家族信託は、認知症対策といった特定の目的のために、ご家族に財産を託し、その管理・運用・処分を委ねる方法です。ここでは、家族信託の仕組みについて分かりやすくご説明します。
| 家族信託の仕組み

財産の所有者(委託者)が、財産を管理・運用・処分するご家族(受託者)に「信託財産」として託すことで、家族信託が成立します。
受託者は、委託者から託された信託財産の管理・運用・処分を行う義務を負い、その中で得られた利益を受益者が受け取るという仕組みです。受託者が信託財産の管理・運用を行うことが難しい場合には、処分(売却)することも可能です。
この時、「受益者」と「委託者」は同一人物であっても構いません。家族信託では、親(委託者)が子(受託者)に信託財産を託し、親(受益者)が利益を受け取るといったケースが多く見られます。
| 親の財産を子に託す理由
「信託財産の管理・運用・処分を子に任せ、得られた利益を親が受け取る」という仕組みが注目されている背景には、日本における認知症患者数の増加があります。認知症になると、記憶障害によって財産の存在を忘れてしまったり、理解力・判断力の低下によって詐欺に巻き込まれたり、不利な契約を結んでしまう可能性があります。
このような危険性から認知症の方を保護するため、各企業の規約や法律によって、認知症の方は金融機関の口座からの預貯金の引き出しや各種手続きが制限されています。しかし、このように制限されていると、不動産を売却したり、生活費を賄ったりすることができません。そこで、家族信託という仕組みを利用し、受託者が財産を管理・運用・処分することで、「自分の財産が生み出した利益を自分が受け取る」という認知症の方にとっては難しいことを可能にしました。
ただし、家族信託も契約ですので、委託者が認知症を患ってからでは利用することができませんので、注意が必要です。
| 家族信託までの流れ
01. 信託内容と目的を決める
家族間で話し合い、どの財産を信託財産にするのか、どのような目的で、誰が受託者になるのか、受託者の出来ることと出来ないことを明確にし、具体的に信託内容を決めましょう。家族信託は信頼の上に成り立っているので、ご家族皆様の納得感が不可欠です。
02. 信託契約書を作成する
話し合いで決まった内容に基づいて契約書を作成しましょう。インターネット上にある契約書の雛型をダウンロードし、自分で作成することもできますが、多額の財産の管理や処分に関わる契約なので、専門家とともに作成することをお勧めします。信託契約書を確実に有効なものにするために、公正証書で作成することもできます。
03. 信託口口座を開設する
受託者は、委託者から託された信託財産と自分の財産を区別して管理する必要があります。特に、金銭の信託を伴う場合には、普段使いしている口座とは別に、信託金銭を管理する専用の口座を持たなければなりません。家族信託のための口座である信託口口座を開設できれば良いですが、開設できる金融機関は限られているので、開設できる金融機関が身近にない場合は、既に開設している口座のうち、使っていない口座を家族信託専用の口座にすることもできます。
04. 信託登記を行う
受託者が委託者から不動産を信託財産として託された場合、その不動産が信託財産であることを登記しなければなりません。信託登記を行っていないと、自分のタイミングで不動産を売却できなくなってしまうので、専門家に相談しながら必ず信託登記を行いましょう。
05. 家族信託の開始
上記の手続きを経て、家族信託が開始されます。










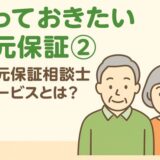
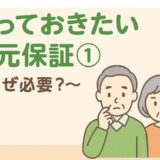

コメント