遺言書とは、亡くなった方が生前に最後に残した意思を書面にしたものです。遺言書がある相続では、相続人は遺言書の記載に従って手続きを進めることができるため、トラブルが起こりにくくなります。そのため、生前に遺言書を作成しておくことは、相続人にとって大きなメリットとなります。この記事では、遺言書の作成を考える際に、押さえておきたいポイントを簡単にご説明します。
1. 公正証書での作成が安心
遺言書には大きく分けて2種類あり、ご自身で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は、自分ひとりでいつでもどこでも作成できるというメリットがある一方で、遺言書の形式といった法的な要件を踏まえて作成しなければならないというデメリットもあります。そのため、法的に認められない遺言書を作成してしまう可能性があります。遺言書が法的に有効かどうかは、実際に相続が発生して遺言書を使用するタイミングにならないと分からず、作成した遺言書が使用できないという状態になりかねません。一方、公正証書遺言であれば、証人手配の手間や費用はかかりますが、弁護士や検察官の経験がある方からなる公証人が作成してくれるので、形式の不備がなく、法的に有効な遺言書を作成することができます。
2. 遺言執行者の指定
遺言書はご自身の死後に有効になる書類なので、当然ながら作成者が遺言内容通りに相続を実行することはできません。そのため、相続人の皆さんが協力して遺言による相続を実行する必要がありますが、多くの書類の取得が必要であったり、遺贈の指定がある場合にはそのための手続きをする必要があったりと、相続に慣れていない方だけで進めていくのは大変難しい作業です。相続人がこうした負担を負うことなく、スムーズな相続を遂行できるよう、遺言書では、遺言内容を実現する権利と義務を負う「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者は、破産者や未成年者でなければ誰でもなることができ、相続人に負担をかけることなく、遺言者ご自身の意向を確実に実現できます。
3. 分割方針は遺留分の考慮も必要
遺言書では、遺言者が自由に遺産分割の方法を指定することができますが、特定の相続人には最低限の相続分が保障される権利、「遺留分」があります。仮に遺言書で指定された方法で相続を行った結果、その相続額が特定の相続人の遺留分を下回っている場合は、その方は「遺留分侵害額請求」を行うことによって、侵害された遺留分を回収することができます。相続人のトラブルを回避するために作成した遺言書が、かえってトラブルの原因にもなりかねませんので、各相続人の遺留分も考慮した上で、分割方法を示すようにしましょう。


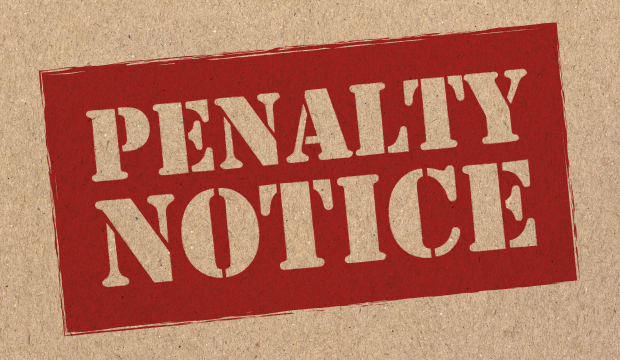



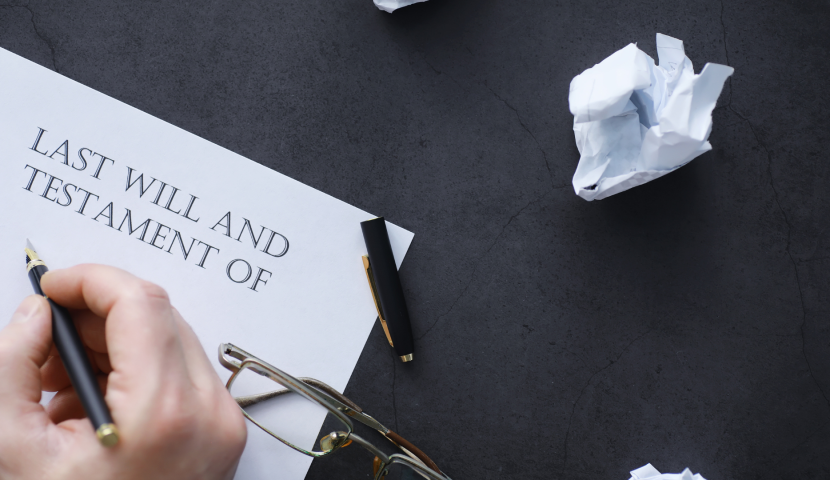


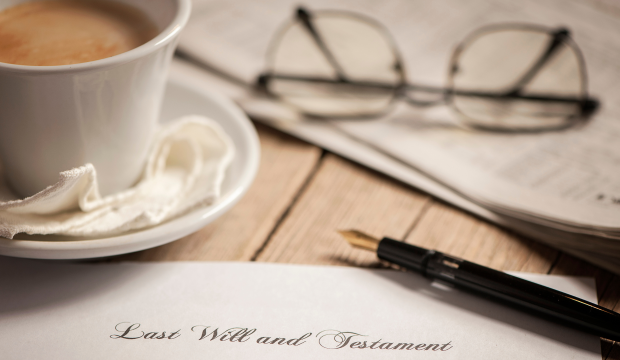
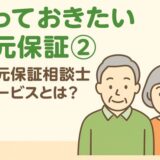
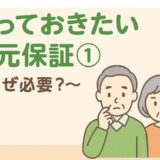

コメント