相続税とは、亡くなった方が所有していた財産を相続人が受け継ぐ際に、その受け継いだ財産に対して課税される税金です。相続税には基礎控除というものが設けられており、実際の遺産総額がこの基礎控除額を超えなければ、相続税を納める必要はありません。相続が発生した場合は、まずご自身が相続税申告を行う必要があるかどうかを確認しましょう。
| 基礎控除について

相続税は、全ての人が納めるわけではありません。遺産総額が基礎控除額を超えた場合にのみ、相続税申告が必要になります。遺産総額が基礎控除額を超えない場合は、申告の必要はありません。もし相続税を納める必要がある場合は、相続税の控除や特例などを利用できる可能性がありますので、事前に確認しておきましょう。基礎控除額は、以下の計算式で計算できます。
相続税の基礎控除額の計算方法
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
| 相続税の計算の流れ
相続税は「申告納税制度」を採用しているため、財産評価から納税まで自分で行う必要があります。各相続人が納めるべき相続税は、以下の流れで計算することができます。
遺産総額
遺産総額 = 相続財産 - 非課税財産
基礎控除額
基礎控除額 = 3000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )
課税対象となる総額
課税対象額 = 遺産総額 - 基礎控除額
各相続人の税額
各相続人の相続税額 = 相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額
| 控除・特例
相続税には、控除や特例が設けられており、相続税の課税対象や相続税額を減らすことができます。前述した基礎控除以外に、小規模宅地等の特例や配偶者控除、障がい者控除などがあります。
| 期限とペナルティ
親族の方が亡くなり相続が発生した際に、遺産総額が基礎控除を超え、相続税申告が必要な場合は、申告・納付の期限はどちらも「自己に相続のあったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。
期限内に申告・納付を行えなかった場合や、申告内容に誤りがあった場合は、ペナルティが課せられ、過少申告加算税や無申告加算税、重加算税などが科せられます。
| 修正申告と更正の請求
相続税の申告・納付は期限内に行う必要がありますが、様々な理由により期限後に申告内容を修正することもあります。納付額が本来の納税額よりも少なかった場合は、修正申告をすることで追加で税金を納めます。納付額が本来の納税額よりも多かった場合は、更正の請求をすることで、納め過ぎた相続税の払い戻しを受けることができます。


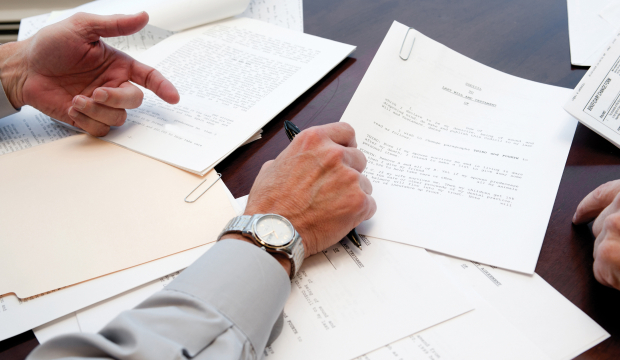

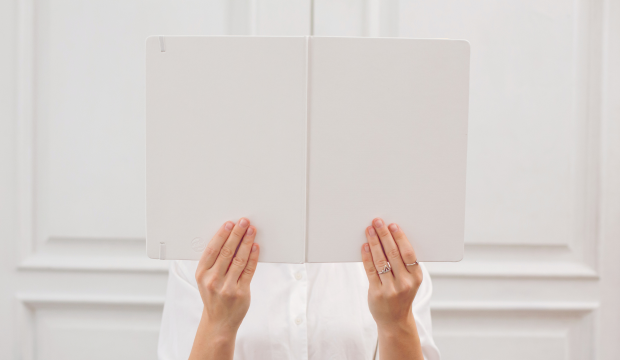





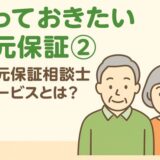
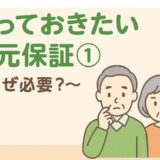

コメント